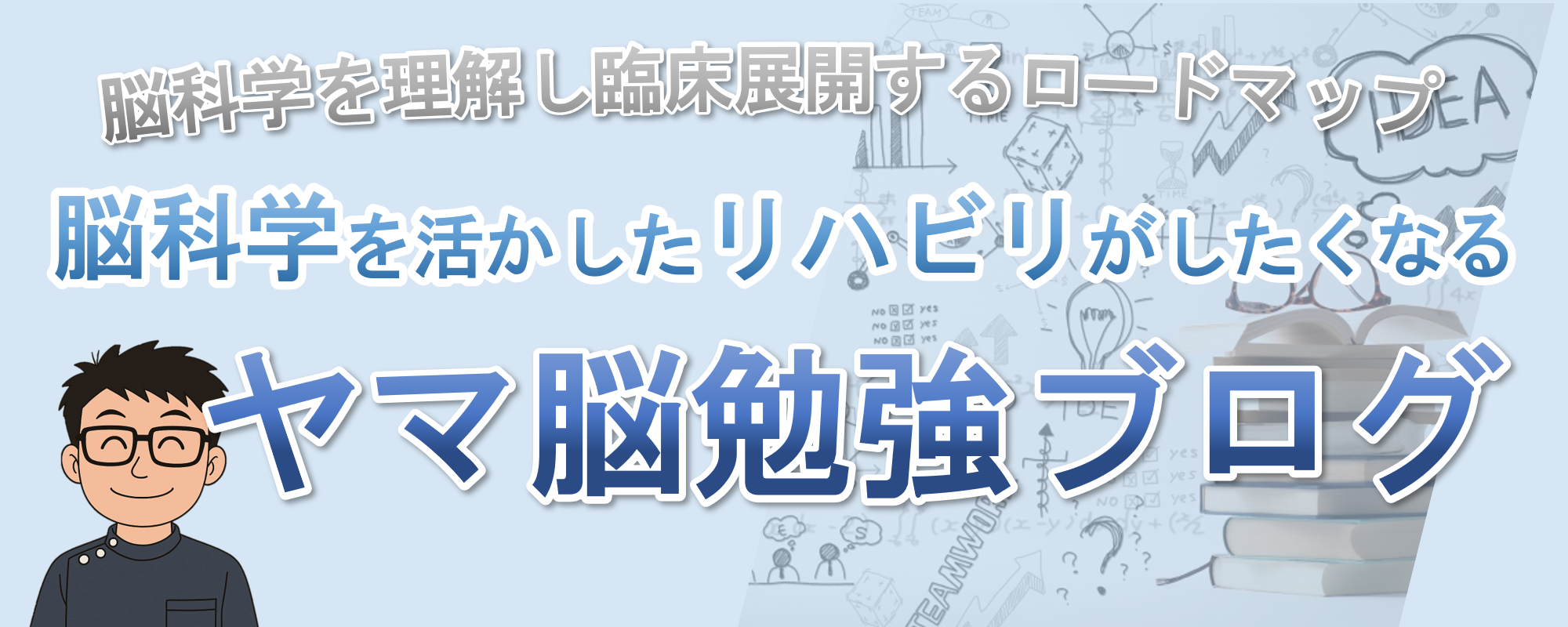皆さん、こんにちは!
こちらでは初学者でも理解できる脳科学の勉強方法をお助けしていきます!

脳科学に興味があって勉強しようと思ってるんだ!
でも、どうやって何から勉強を始めていいかわからないから教えて欲しいな~

よっしゃー!
私も最初は全然わからなかったけど、だからこそ初心者でもわかりやすいロードマップを教えていくで~。
ヤマのプロフィール
理学療法士を志したきっかけ
大学生の頃の私は、サラリーマンよりも体を動かす仕事がいいな~という理由だけで、介護士の仕事に就こうと考えていました。
そして、通信教育を通じて介護福祉士の資格を勉強している時に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というリハビリの仕事があることを知りました。
この時は、「へぇ~そういう仕事があるんだな~」って思ってただけで、素通りしていました。
そんなある日、理学療法士になる!と決意する瞬間が来ます。
デイケアで軽度片麻痺の利用者さんの歩行練習に付き添っている時、利用者さんから
「どうしたらもっと上手に歩けるようになるの?」
これを聞かれた時に、確かにどうすればいいんだろう?適当なことは言えないし…
と、無言のまま何も答えられませんでした。これがきっかけです。この時は、答えられなかったことに申し訳なさを感じていました。
これを機に、自分は歩き方などの基本動作で困っている人の力になろうと決心しました。
脳卒中のリハビリに興味をもった理由
お金がなかったこともあり、働きながら学校に行くしかなかったため、夜間部の学校に行くしかないと決めていました。
何とか勉強を頑張り、希望の夜間部の学校に通えることになりました。
昼は、デイケアで働き、夜は学校という生活を3年間続けました。
そしてある日、昼働いているデイケアの脳卒中の利用者さんが一生懸命麻痺した手を健側の手でつかんで持ち上げるリハビリを頑張っている場面に遭遇しました。
その利用者さんがデイケアで働く先輩PTに
「どうしたらこの手は動くようになりますか?」
と聞いていました。
それを聞いた先輩PTは、
「もうプラトーだからね~」と一言
えっ?そうなの?
衝撃的な一言でした。利用者の希望が消えたと共に自分の中で何かが芽生えました。
「プラトーって言葉だけで片付けて言い訳ないやん!」と本気で思いました。
本当にこれ以上よくならないのか?何か方法はあるはず!と、その時は、根拠がないモヤモヤだけが残ったのを今でも覚えています。
あれから、脳の基礎研究で、脳には可塑性があることや維持期でも回復(運動学習)により、基本動作や日常生活動作が改善することなど、”6ヶ月でプラトー”になるという昔の常識とされていたことは覆されています。
常に「努力の可能性は無限大にあるはず。」ということを座右の銘にして生きてきました。
私たちは、医療者です。勉強していくことは必要です。
私たちが、改善の可能性を考えていなかったら、脳卒中の当事者の方にとって本当に良いリハビリやケアをすることはできません。
ヤマのプロフィール
回復期病院を経て、急性期病院で脳卒中理学療法士として働いています。
後輩指導で臨床のお助けをしながら、
私自身も勉強会や学会発表を継続して日々ブラッシュアップの日々を続けています。
▶毎年学会発表を行い、外部講師・学会シンポジスト経験あり。論文3本。
▶得意分野は、脳血管疾患、整形外科疾患です。
脳勉強ブログを立ち上げたきっかけ
国家資格に合格して夢をもって病院や施設に入職しても、熱心な指導者がいなかったり、一人職場だったということもあります。
現状、熱心な指導者がいてもできるだけ残業や居残りをしてはいけないという風潮も強いところも多くなっています。さらに、働き手が少なく仕事量に圧迫され、指導したくても指導する時間がなかったり、見て学ぼう!とほぼ放置されているということも聞きます。
せっかく熱意があってもそういう場所にいると、不思議と熱意の炎は消え、周りに流されていってしまいます。そうなると熱意の炎は…
一度消えるとその熱意を燃やすのは一苦労です。
そんな方のお助けになればという想いでブログを立ち上げました。
当ブログのコンセプトは、
「脳科学を活かしたリハビリがしたくなるブログ」です
一人でも熱心な方が増えることで、脳卒中になられた方の希望に沿えることができる人材が増え、結果、間接的にたくさんの方の支援につながると信じています。

私のプロフィールを最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも脳を勉強していきたい方の力になりたいです。
初学者でも一歩ずつ理解できるように、丁寧に勉強方法を教えているので、是非参考にして下さいね!
ブログは少しずつ更新していくので、お楽しみに!
運営者について
若い医療職員、介護職員の方、いつも大変な仕事ありがとうございます。希望や夢を実現するために入職したのに、指導は業務的なことばかり。調べることは多いし、何から手をつけたらいいかわからない。本当は、脳について勉強して、脳卒中の方の力になりたいのに…
と、お悩みの方ご安心ください。
当サイトは、医療従事者や介護従事者、脳科学を勉強したい方に向けたコンテンツです。
特に初学者で、勉強したいけど勉強方法がわからない、どんな書籍で勉強したらいいのかわからない方に向けて情報発信を続けていきます。
脳科学は、脳血管疾患のみならず私たちの対象者が”ヒト”である限り、必須の勉強だと感じています。
普通のPTだった私が脳科学を勉強し、臨床で成果を出し講師として登壇できるまでのロードマップをわかりやすく解説していきます。
当サイトについて
私たち医療従事者にとって、医療は日進月歩であり日々アップデートが必要な仕事です。
ただ、勉強して知識を得ても、それを臨床に活かせなかったらただの自己満足で終わってしまいます。
現在は、ネットやSNSですぐに情報が得られるメリットがある一方で、情報があふれ過ぎています。
正しい情報を理解し、臨床に展開していくためには、まずは本から学ぶことが重要と考えています。
そのため、脳科学に興味があって勉強していきたい初学者の方に向けて、当サイトを立ち上げました。
一歩ずつ日々の臨床力を上げて、対象者の笑顔に繋げるために一緒に勉強していきましょう!
なんで”脳科学”なの?
医療の中でも、脳科学に特化して勉強方法を情報発信する理由は、脳科学は難しいけど、勉強するメリットがたくさんあることと、”ヒト”を理解するための最適解のうちの1つだからです。
私たちは日々の臨床の中で、認知症の方、脳卒中で運動麻痺や感覚障害のある方、高次脳機能障害を抱えた方など、さまざまな対象者と向き合っています。
そうした場面で、
・なぜ認知症になると記憶障害と感情や性格変化のパターンがあるのか?
・なぜ対象者は頑張っているのに、麻痺した手足が動かないのか?
・なぜ、意欲がなくなりリハビリに前向きになれないのか?
こうした疑問に対して、脳科学を学ぶことは大きなヒントを与えてくれます。
脳科学を勉強するメリット
すべての対象者は”脳”を使っている
・身体機能の回復も、認知機能の維持も、日常生活の意思決定も全て脳の関与がある
・脳科学の理解は、対象者すべての理解に繋がる
・医療従事者にとって脳科学の知識は強力な土台となる
症状の背景を理解し、アプローチすることができる
・認知症による記憶障害や性格変化の背景を理解し、説明することができる
・運動麻痺や感覚障害の原因を把握し、機能回復に向けた介入を考えることができる
・高次脳機能障害の症状(注意・記憶・遂行機能など)に対して、より自信をもって対応することができる
・高次脳機能障害の対応の仕方が変わり、より対象者に寄り添った支援を行うことができる
対象者との信頼関係を築きやすくなる
・脳の働きに基づいて「なぜこの練習を行うのか」をわかりやすく伝えることができる
・対象者にとって納得感・安心感が生まれることで、より信頼関係を築くことができる
多職種やご家族への説明力が上がる
・医師や多職種との情報共有や連携がスムーズになる
・脳画像から身体、認知機能、高次脳機能の症状を推測することができる
・機能障害についての予後予測を考えることができる
・ご家族に対して、対象者の接し方について丁寧な説明をすることができる
”困った行動”の理解が深まり、共感が生まれる
・暴言や拒否、意欲低下といった行動についても脳の影響から生じたものと理解できれば寛容になれる
・上記の対応力の質の向上に繋げることができる
教育や指導にも活かせる
・実習生や後輩に対して、「なぜこの評価が必要なのか?」「なぜこの課題・介入なのか?」を自信をもって伝えることができる
・方法論ではなく、”なぜ”を伝えることができるので、臨床教育の質が高めることができる
自分の理解力・判断力が磨かれる
・脳科学を学ぶことで、論理的思考・因果関係の理解・科学的根拠に基づく視点が養うことができる
・臨床の中で”経験や感覚”ではなく、根拠に基づいた思考による判断力を身につけることができる
自分自身の行動や感情も理解し、成長にもつながる
・自身の生活で習慣化やモチベーション、集中力のつけ方を理解し実践することができる
・感情のコントロールやストレス対応に活かせることができる
・脳科学を知ることで学習効率を高めることができる
他分野との接点や視点が広がる
・脳科学を勉強することで、心理学・教育・AI・ロボット工学などさまざまな分野へ視野が広がり、介入方法の発想が広がる
行動あるのみ!
時間がない方も大丈夫です。
毎日10分のすき間時間を作るだけで、年間60時間以上勉強することができます。
これを3年間続けたとなると、180時間以上になります。
年間0時間の医療従事者とでは、どちらの方が信用できるか?
大きな差が出ていることは火を見るよりも明らかですね。

私も日々、勉強中です!一緒に勉強を頑張っていきましょう!
以上、ヤマでした~
どうぞよろしくお願いいたします。